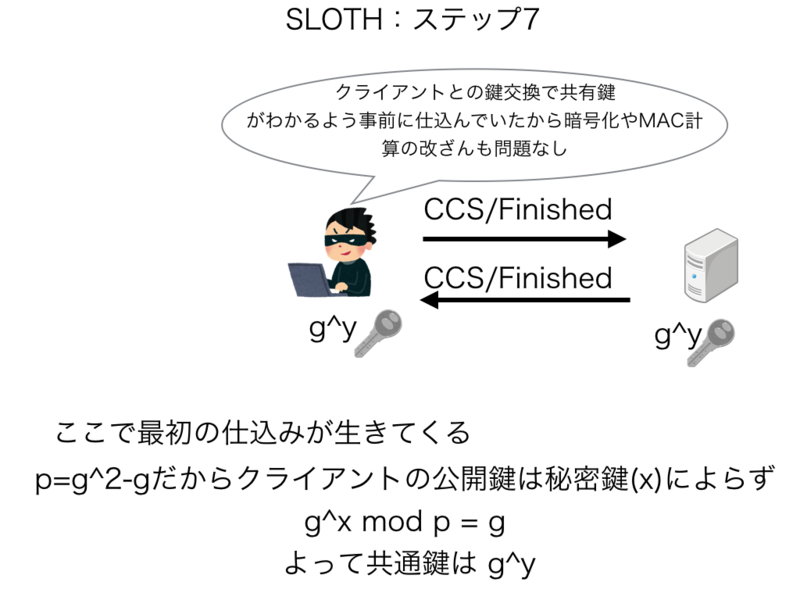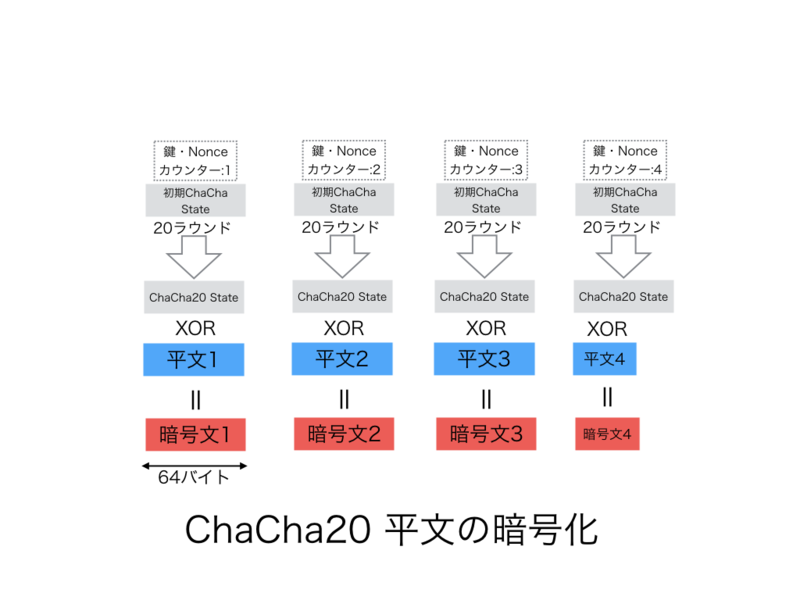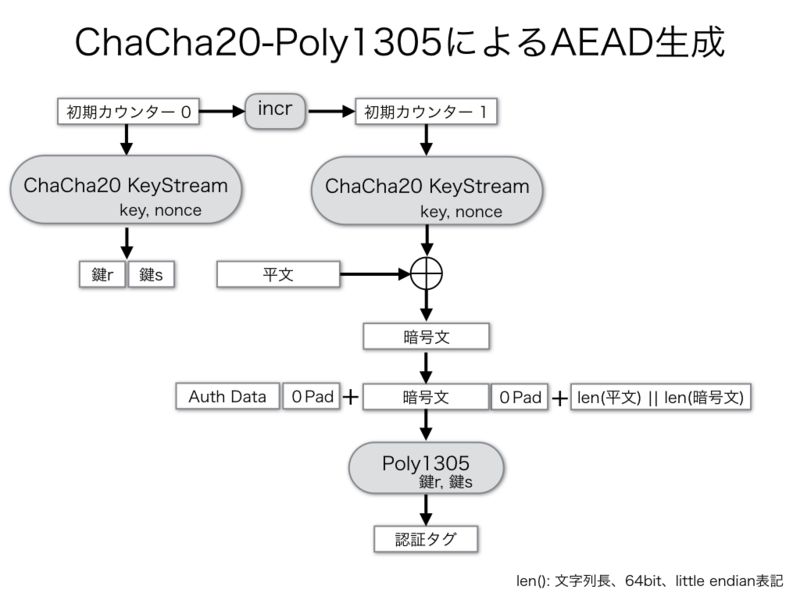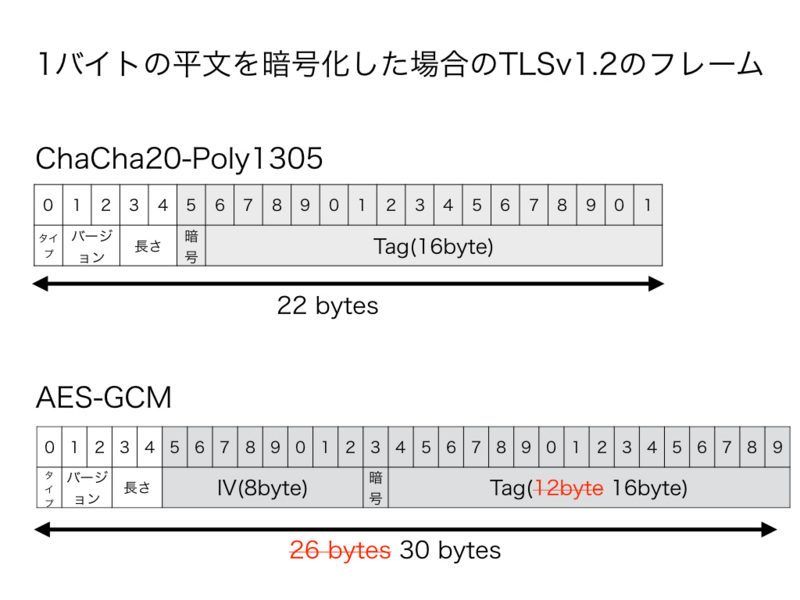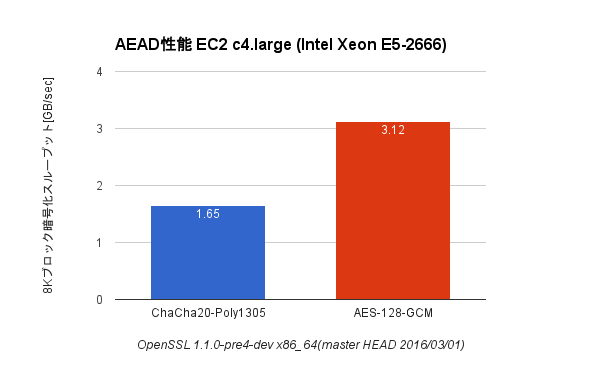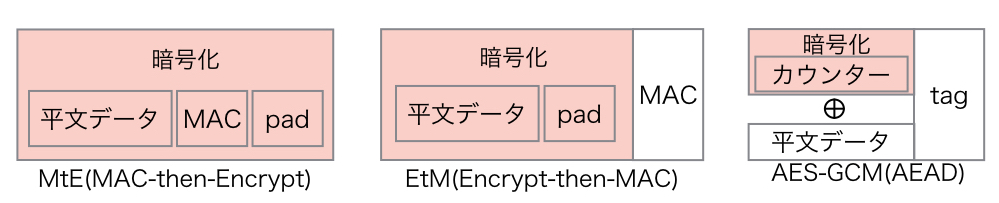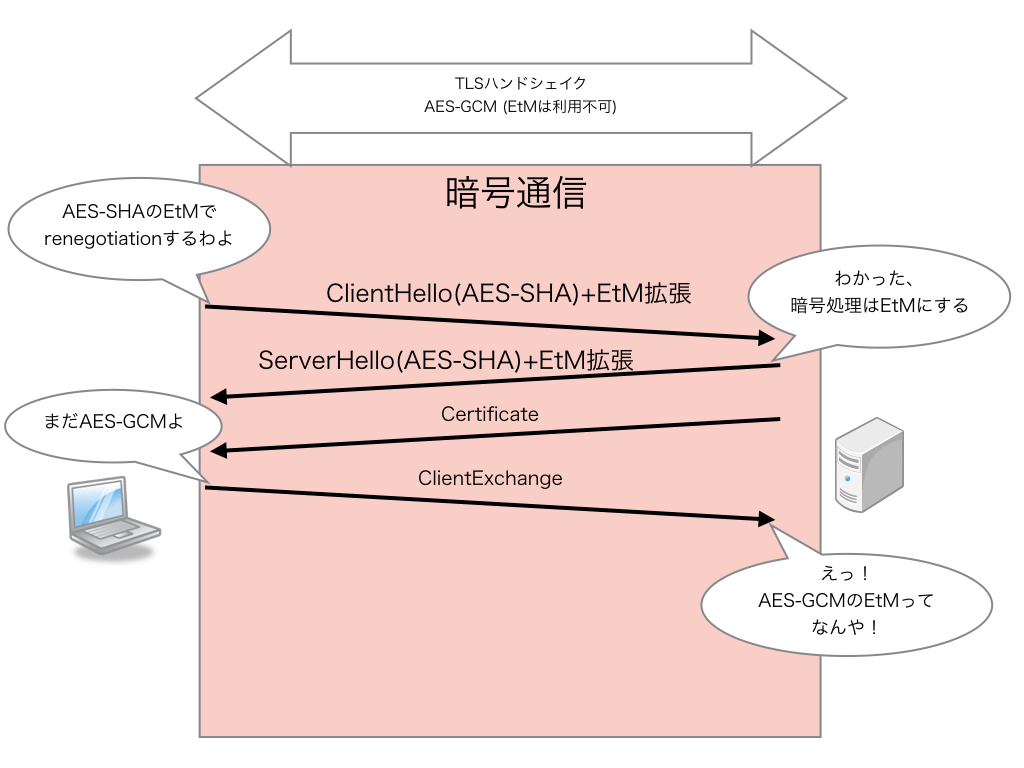ごめんなさい、書いてたら長くなってしまいました。長文嫌いな方は避けて下さい。
鹿野さんの名前を間違えてました。大変失礼しました。(_O_)
1. はじめに。日本語翻訳版刊行によせて、
昨年10月、Vさんから
「 Bulletproof SSL and TLS翻訳本のレビューします?時雨堂が出資してる出版会社が翻訳権を勝ち取ったのです。」
とお誘いを受けたのが、そもそもの始まりでした。
「とうとうあれの日本語翻訳が出るのか、でもホント大丈夫か? 内容の濃さもさることながらあの分量とクオリティ、記述の正確さや厳密さに対して特に高いものが要求されるセキュリティ分野。しかも初心者向けではないエキスパート向け。この本の翻訳を出すとは… なんと大胆、少し無謀なことではないか?」
との思いが正直頭をよぎりました。
自分もちょうど17年半勤めた前職を辞めて転職した直後。新任早々こんなことしても許されるのか? 恐る恐る遠慮がちに上司に伺ったところあっさりOKの返事。さすがっ、理解のある上司で良かった、ホント感謝します。
編集の鹿野さんからの依頼は、
「レビューについては、一文一文を集中的にではなく、ざっと見ていただくようなものを」
と控え目なもの。
「いやいや、この本をざっくりレビューじゃ失礼です。じっくり見させていただきます。」
と、少し自分にプレッシャーをかけつつ読み始めました。
そして一晩作業してみて私からの返事。
「第一印象として、まだ日本語訳としてこなれてない部分が多いなと思いました。特に2章で技術的に難しい記述になると英文の表現に引きずられて日本語の文意が取りづらいなと感じる部分が多くなりました。
日本語訳を読みながら詰まったり、気になったところにコメントを差し込んだのですが、結局29ページで100個近くのコメントになってしまいました。」
まぁ正直な感想です。でも、これじゃ全然先に進まない。
幸いに、技術的に間違って訳している箇所はかなり少なく、ちゃんと内容を理解して翻訳がされているのがわかります。これならきっと原書のクオリティを保ったまま翻訳本にできるはず、そう確信しました。
しかしその後、何章か同じペースでコメントを入れ進めたのですが、そのうち本業の方が立て込んでしまい途中でレビューが止まってしまいました。すみません。
その間、鹿野さんから私のコメントに対する返事を頂いたのですが、驚いたことに監訳の方に丸投げするわけではなく、ちゃんとご自身で判断されて修正対応されてます。私のコメントが間違っていることもしばしばで、逆に鹿野さんから指摘を受ける始末。恥ずかしい。あれっ?エンジニアの方が編集者してるんじゃないか?マジそう思いました。
そんなまま数ヶ月経った後、「原稿を更新しました」とのご連絡。うぅ、うっかりメール見落としてた。直ちに未レビュー章を片付けないとまずい、早速レビュー開始。すると、
「あれっ、めちゃくちゃ読みやすい。この章のレビューコメントがゼロ。」
「うそ、以前ならそんなことはないはず。おかしい。」
「時間をおいてもう一度読み直そう。」
翌日、「やっぱりゼロだ。何が起きたんだ?」
鹿野さん曰く、「思い切った編集方針に切り替えました。」
すごーい! 読んで進む、進む。あかん、このままじゃ本当にレビューしているのか疑われてしまう。そういう心配してしまうくらいの素晴らしい出来になりました。
まぁそんなこんなギリギリまでドタバタのレビューがかかってしまい、ご迷惑をおかけしました。そして無事「プロフェッショナル SSL/TLS」が刊行されました。めでたいことです。
余談はこのぐらいにして早速本の中身について書いてみます。
2. この本の扱う範囲
私は過去2年(2015/16)、セキュリティ・キャンプ全国大会でTLSを教える講義を担当してきました。各地から集まる若く優秀な学生さんに対してTLSをどう教えるのか、最も悩むところです。
結局はいくら悩んでも、TLSのハンドシェイクの仕組みを学んでもらうことに落ち着いてしまいます。やっぱりTLSは難しい。
TLS仕様(RFC5246)自体は、ハンドシェイクやプロトコルフォーマットを規定するだけで、実はX.509証明書などPKIやAES、RSAなど暗号技術の仕様については、TLSで具体的な中身はほとんど含まれていません。これらは他への関連仕様として参照されており、IETFで扱うWGも違います。
後ろ髪引かれるのは、狭義的(RFC5246)な見方では、キャンプではそれらを外部仕様としてTLSを支える土台としてスコープ外にせざる得ないことです。時間的にも、キャパ的にも、全部盛り込むのは無理があります。なので最終的にはこのスライドでごまかしています。
![f:id:jovi0608:20170317015704j:plain f:id:jovi0608:20170317015704j:plain]() それに対し本書では、これら全部引っくるめてTLSセキュリティを解説しています。いやさすがです。
それに対し本書では、これら全部引っくるめてTLSセキュリティを解説しています。いやさすがです。
本書では、上図の各項目に対応する章として、
TLSのセキュリティ:
「第2章プロトコル」、「第6章実装の問題」、「第7章プロトコルに対する攻撃」
暗号技術:
「第1章SSL/TLS と暗号技術」、「第6章実装の問題」、「第7章プロトコルに対する攻撃」
乱数生成:
「第6章実装の問題」、「第7章プロトコルに対する攻撃」
「第3章公開鍵基盤」、「第4章PKIへの攻撃」
「第8章デプロイ」
な関係になります。
全部を網羅するので扱う技術領域の幅が一気に増え、それぞれが深い内容を含みます。 まぁどんな専門家でも頭でわかっているつもりなだけで、いざちゃんとした成果物まで仕上げるとなると並大抵の労力ではすまないでしょう。
しかも、さらに私の講義の範囲の図にも入っていない、
上位レイヤー(HTTPS)のセキュリティ:
第5章HTTPブラウザ問題、10章、HSTS、CSP、ピニング
性能:
第9章 パフォーマンス最適化
までカバーしている。あぁもう凄いですね、と感服するしかありません。
既に本書を購入し読み始めた方は、その広大な技術領域と膨大な量に圧倒される人も多いかと思います。
個人的には、これから1章から読み始めることにしても、必ずTLSの技術領域に関する土地勘を意識することが大切だと考えます。ざっと読む部分・深く精読する部分などを決めて、ある程度メリハリのある読み方をすることをお勧めします。
3. この本の凄いところ
話がそれますが、実は先日社内から依頼を受けて「技術のスキルアップ、私のやり方」というセミナーを内部で開催しました。
自分のこれまでの取り組みを振り返りながらあれこれメンバーと共に話をした実に楽しい時間でした。その中で「アウトプット方法 ブログの書き方」というセッションを設け、某メンバーのブログのビフォー・アフターを紹介しながらブログの書き方やアウトプットの重要性などの話をしました。
その時のスライドの一部がこれです。
![f:id:jovi0608:20170317015711j:plain f:id:jovi0608:20170317015711j:plain]()
![f:id:jovi0608:20170317015718j:plain f:id:jovi0608:20170317015718j:plain]() 自分が思うに、今回の本はまさにこれなんですよね。
自分が思うに、今回の本はまさにこれなんですよね。
この本に対して私のスライドを比較するのはほんと失礼だと思いますが、この本の凄いところをこの図に関連付けて書いてみます。
3.1 凝縮された内容
序文で著者自身がこの本の目的を
「著者が時間をかけた分読者の時間は節約できるよう、著者が知っていることの中でも特に重要な内容を詰め込み、僅かな時間で同じ内容を理解してもらうことである。」
と書いています。
まさに「特に重要な内容」を詰め込んでおり、上図の様におそらく著者はこの10倍、もしくはそれ以上の分量を調べ上げているはずです。その中から著書のコンテキストに合わせて絞り込み、体系化した内容にして書いているのだと思います。
この作業自体は他の本でも行われており、特別なことでもないでしょうが、TLSやPKIなど過去20年分しっちゃかめっちゃかした技術領域を広く網羅した範囲で行ったのは凄いです。
この本を購入することは、TLS/PKIに関連に重要な情報に辿り着くまでの調査とそれを理解するための時間を買っていると思って良いです。ただ本当のエキスパートを目指す人は、ここに書いてあることが全てではなく、この裏に広大な技術領域が広がっていると思って下さい。
また11章以降は各実装の使い方になっていますが、これは「実際に検証して確認(エピソード記憶)」に該当する作業です。これまで学んだことが実際どう設定に反映されるのかここで結びつけることができます。私が思う本当に理想的なアウトプットだなと感心します。
3.2 何事にも代えがたい一次資料へのポインター集
私は原著を所有していますが、実はこれまであまり中身を通して読んだことがありませんでした。使う時は、なにか調べ物をする時です。
新しい脆弱性情報が公開されると全て新規のものは稀で、大概新しい手法に過去の脆弱性を組み合わせたり、改良したりしたものが多いです。その際はこの本が大活躍します。関連するインシデントや脆弱性を楽に探すことができ、その一次リンクが脚注に数多く掲載されているからです。
日々発生する脆弱性やインシデント情報。いくらブックマークしていても少し経つところっと忘れてしまいます。検索で探し当てるにしてもS/N比が悪く効率的ではありません。すっかり忘れてしまった自分のブログに助けられることもしばしば。
この本は本当に一次情報にこだわっています。書いてある内容・図・データも、その多くが一次情報からのエビデンスがあるものということがはっきりわかります。この一次資料へのポインターは、何事にも代えがたい情報です。
これに加え、最新のTLS/PKIの動向や脆弱性の情報は、Bulletproof TLS Newsletter で受け取ることができます。近うちに商品ページからリンクが貼られるようです。毎月1回程度TLS/PKI/暗号技術などの最新情報に関する簡単な 解説やリンクがメルマガのニュースレターとして配信されてきます。普段いろいろアンテナを張っているつもりでも結構見逃しているものが多々あり、このニュースレターで助けられることも多いです。この本を読んで知識を得た方は、是非これで最新情報を得て下さい。
4. 個人的に思う注意点
良い事ばかり書いても書評にならないので、いくつかレビューしていて気づいた注意点を。
4.1 11章以降の実装バージョン
11章以降の実装で解説しているソフトウェアは最新のバージョンに追随していないものがあります。
特に OpenSSL は 1.0.1 をベースとしており、1.0.1 は昨年末にサポートが切れています。手元で試すならぜひ 1.0.2 を使いましょう(実は一部OSディストリビューションではそのまま自社サポートの範囲内で継続利用しているところもありますが、個人的にはあまりお勧めしません)。
ここで書かれているopensslコマンドや出力には、1.0.2でも大部分は違いはありませんが、cipher suite系は異なっている場合があります。
特に本文で解説されているFREAK攻撃などにより輸出グレードCipherは全てdisableされています。さらにSLOTH攻撃の影響でSSLv2も完全に削除されています。
最近では LOW cipher もなくなっており、本書で記述されている出力結果と異なる場合もありますので注意して下さい。
翻訳版は原著のフォークをせず、原著の更新を待つというポリシーですので、しばらくは更新を待ちましょう。
4.2 文書による解説の限界
ここ数年 Inria と Microsoft Research のジョイントでFREAK, Logjam, SLOTH などTLSに対する非常に高度な脆弱性の発見と公開がされてきました。
私は原論文を読んでいたので、翻訳文を読んでいるときでも「あぁこの部分はこういう記述にしたのか」とか「これはこのことを指しているな」といったことを思いながら読むことができ、それほど違和感を感じませんでした。その記述は正確性を犠牲にせず、どこまでわかりやすく書こうとしているか、著者の工夫が見られるからです。
しかし、ふと訳文だけしか読んでいない読者だとどこまで理解ができるのかな?と少々不安に思いました。
特に「7.6節 トリプルハンドシェイク攻撃」は、理解するのに最難関の部類に入るものです。
これは翻訳の出来、不出来のレベルではなく、実は容易な文言で解説するにはこの辺が限界じゃないかと思えてしまうほどです。
Face-to-Faceの講義や動画アニメーションなど駆使すれば、なんとか読者にも理解してもらえるかもしれませんが、文書だけではどうでしょう? これ以上もっとわかりやすく書いて読者に伝えることができるか?自分でも全く自信がありません。
これらの部分は、一度読んでもわからないからと言ってあきらめず、是非原論文にでもあたって欲しいなと思います。
4.3 秘伝のタレのような内容
原著は、発行後も更新されています。なので記載の時期によって微妙に記述の仕方が変わっている部分もあります。
もちろん技術的な整合性は取れているので問題はないのですが、RC4の危殆化やBEAST攻撃に関する部分など前半と後半で微妙にニュアンスが違っているなと読んでいて感じるところもありました。
他にも、著者の過去ブラウザの挙動の改善にいろいろ取り組んだ時の経緯で、ブラウザのインターフェイスには結構厳しい表現で書いているところも見られました。この点、著者の努力の甲斐があってかこの領域、最近ではブラウザベンダー側の改善が著しい分野です。特に「5.7 セキュリティインジケーター」で記載されているセキュリティアイコンの変更に関しては、翻訳本では最新ブラウザの画像を使っています(本文の更新自体は原著通りです)。これも今後の改訂が期待されるところです。
頭から読んでいると文書の更新時期が想像でき、まるで継ぎ足しのタレを味わっているようで読んでいて味わい深いです。
5. TLS1.3の改訂に向けて
17章のまとめの文章は、私にとっても非常に考えさせられる文章です。まとめの章は、商品ページに全部が掲載されていますので購入前でも読むことができます。
著者は、
「TLSはこれまで欠陥が多く修正が重ねられてきたが、もともと完璧なプロトコルなどはなく、どんなものも同様の状況になりえる、これまで普及して成功を収めたプロトコルに希望を持とう」
と書いています。
TLSはこれまでの数多くの技術負債を抱え、かつ最大の後方互換が求められ安定的に動作することが求められるプロトコルです。つい先日 SHA-1の衝突耐性が破られました。 md5の歴史から2nd-preimage耐性が破られるまでは時間の問題でしょう。SHA-1証明書が今後どういう命運をたどるのか、md5の衝突をついた「4.5 偽造RapidSSL証明書」を読めば予想できます。多大な社会的コストを払ってSHA-2の証明書に移行を進めたのはこういう過去の教訓を踏まえてのことです。今では md5は Flame マルウェア内で衝突計算が可能になるまでになっているようです。
TLS1.3では、様々な機能の廃止や見直しが行われています。中身はほぼメジャーバージョンアップレベルであるため、バージョン名をTLS2.0やTLS4にするか、大きな議論に発展し最終的にTLS1.3のままで決着しました。通常その仕様を読んでもどうしてこのような仕様になったのか、その議論の経緯や理由が明確にかつ詳細に書かれていることは少ないです。
本書を読めば、ここに書いてある脆弱性や攻撃を教訓としてTLS1.3の仕様が決められていることがわかるはずです。更新版が来れば、全てがこのTLSの技術負債を(完全ではないが)かなり一掃するTLS1.3の仕様につながっている、と理解する日が来るでしょう。
最後に、
以上、あまり書評にもならないことをつらつら書いてしまいましたが、実際この本が翻訳本として日本語で読めることは日本のエンジニアにとって本当に喜ばしいことだと思います。
先に書いた通り、ここに書いて有ることは本当に重要なことに絞り込んだ内容であり、それ以外の部分がその裏に隠されています。
ということはこの本を使えば、残りの90%をさぐる非常に良い足がかかりになります。 なのでこの本を教材とした勉強会を近いうちに内部で開始するつもりです。さぁ、メンバーが残り9割をこれからどこまで探ることができるのか、今から楽しみです。